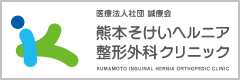元気になるオルソペディック ブログ
研修医が燃え尽きる前に知っておきたい!燃え尽き症候群を防ぐストレス対策と仕事満足度の高め方

【燃え尽き症候群とは?原因と症状を知ろう】
医師として働き始めたばかりの研修医の皆さんは、日々の多忙な業務と責任の重さに直面していることでしょう。そんな中、気をつけたいのが「燃え尽き症候群(バーンアウト)」です。これは、慢性的なストレスにさらされることで心身が消耗し、仕事へのやる気や喜びを感じられなくなる状態を指します。
バーンアウトには、主に3つの症状があります。ひとつは「情緒的消耗感」です。これは、仕事に取り組むエネルギーが尽きてしまい、何をするにも疲れきっている状態を指します。次に「脱人格化」、つまり患者さんや同僚に対して冷淡になり、共感できなくなること。そして「個人的達成感の低下」といって、自分の仕事に価値を感じられなくなることです。
特に救急医療の現場では、患者対応の多さや緊急性の高い判断を求められるため、精神的な負荷が非常に高くなります。今回紹介する研究でも、救急医療従事者は他の職種に比べて高いバーンアウト傾向を示しており、特に「情緒的消耗感」が仕事満足度を大きく左右する要因として挙げられています。
【仕事満足度がカギ!ストレスとどう向き合うか】
燃え尽き症候群を予防する上で、重要なのが「仕事満足度」を高めることです。実は、自分の仕事に満足している人は、燃え尽きにくいというデータが出ています。逆に言えば、仕事にやりがいを感じられなくなった時こそ、燃え尽きのサインかもしれません。
研究によると、「年収」や「家庭の経済状況」が良いと、仕事満足度が高くなる傾向があります。ですが、これはコントロールが難しい要素でもあります。それよりも注目すべきは「感情的な疲労感の軽減」です。たとえば、休憩時間をしっかり取る、同僚と悩みを共有する、時には指導医に相談するなど、身近な工夫が効果的です。
また、「仕事に意味を見出せるか」も満足度に直結します。忙しい中でも「この患者さんの命を救えた」「家族に感謝された」など、小さな成功体験を意識して振り返ることで、達成感を得ることができます。
【燃え尽きないために今日からできる3つの工夫】

では、研修医の皆さんが今日から始められるバーンアウト予防の具体策を3つご紹介します。
1つ目は、「感情を無視せずに、正直になること」です。「疲れた」「つらい」と感じたら、自分を責めるのではなく、まずその感情を認めましょう。メモに書き出すだけでも気持ちが整理され、冷静になれることがあります。
2つ目は、「小さな達成感を積み重ねること」です。どんなに忙しくても、一日の終わりに「今日は〇〇ができた」と1つでも思えるようにしましょう。積み重ねが自信になります。

そして3つ目は、「相談できる環境を持つこと」です。指導医、同期、看護師さんでも構いません。誰かに話を聞いてもらうだけで、悩みが軽くなることは多いものです。
研修医という立場は、責任感が強い分だけ、つい無理をしてしまいがちです。でも、医師として長く働き続けるためには、自分の心と身体を守ることも仕事の一部です。どうか無理をせず、自分を大切にしながら、日々の医療に向き合ってください。
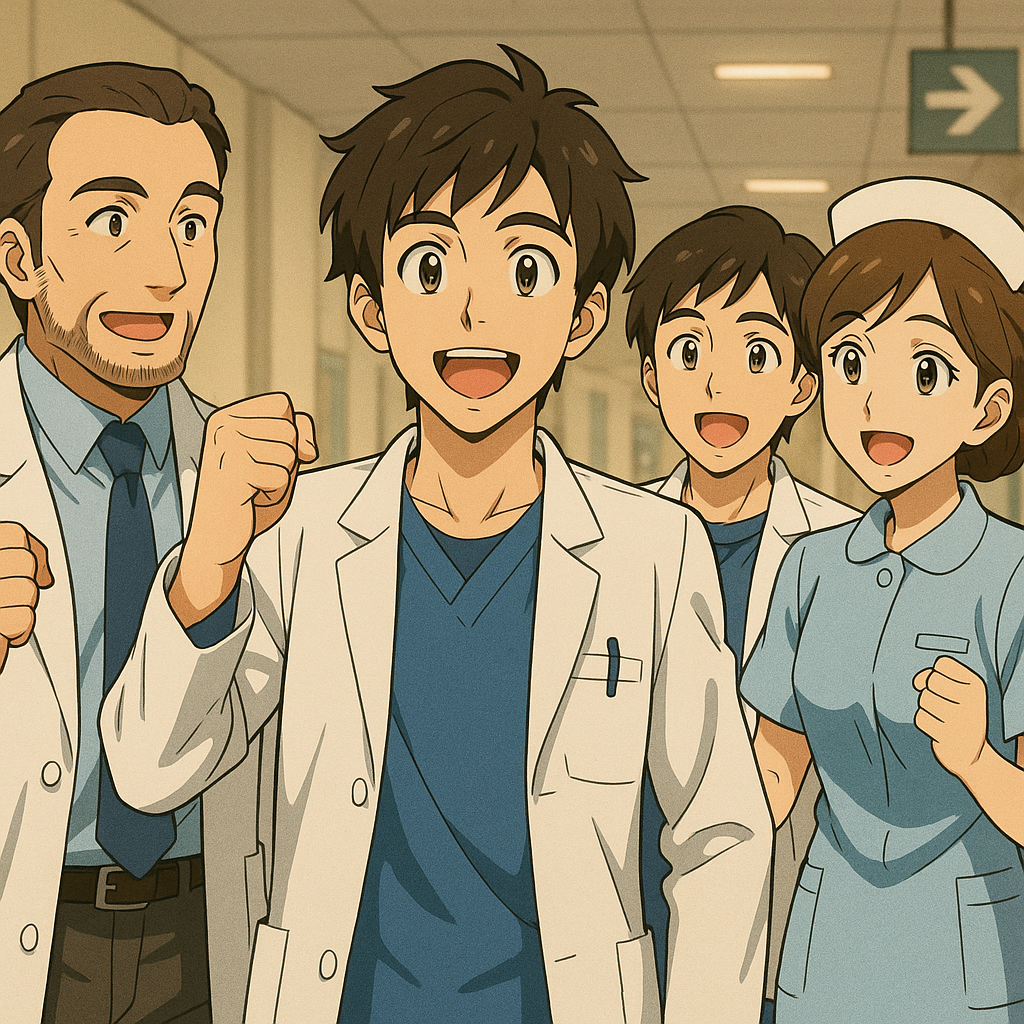
【参考論文】
Tarcan M, Hikmet N, Schooley B, Top M, Tarcan GY. An analysis of the relationship between burnout, socio-demographic and workplace factors and job satisfaction among emergency department health professionals. Applied Nursing Research. 2017;34:40-47.
免責事項
- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。
- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。
- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。
- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。
当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。