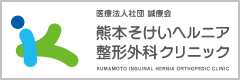元気になるオルソペディック ブログ
小児の再骨折はなぜ起こる?高リスク部位と治療法の違いによる影響を詳しく解説

【はじめに:小児の骨折と再骨折の現状】
子どもの骨は成長過程にあり、柔らかくしなやかな反面、骨折しやすいという特徴があります。
実際、10万人あたり年間163~202件の骨折が報告されており、特に男の子に多く見られます。
骨折後には固定やギプスでの治療が一般的ですが、治療後も骨が完全に強くなっていないことがあり、
「再骨折」と呼ばれる同じ部位の再度の骨折が起こることがあります。
今回の記事では、2025年にフィンランドの研究チームが行った大規模な研究結果をもとに、
子どもの再骨折の発生率やその原因、予防策についてわかりやすく解説します。
【再骨折の頻度と起こりやすい部位】
この研究では、2014年から2023年の間に20,749件の小児骨折を調査し、
同じ部位に再度骨折した「再骨折」が100件(約0.48%)確認されました。
再骨折が特に多かったのは以下の部位です:

- 前腕の骨幹部(橈骨と尺骨):再骨折率 3.76%
- 脛骨の骨幹部:1.01%
- 前腕の遠位部(手首に近い部分):0.55%
- 上腕骨の遠位部(肘に近い部分):0.49%
特に、**前腕の両方の骨が折れた場合(両骨折)**では、再骨折のリスクが最も高くなることがわかりました。
再骨折が起こるまでの日数の中央値は部位によって異なり、
最も短いのは前腕遠位部で約73日、最も長いのは上腕骨遠位部で約426日でした。
【治療法による再骨折リスクの違い】
研究では、骨折の治療方法が再骨折のリスクに大きく関係することも明らかになりました。
治療方法は次の4つに分類されます:
- グループA:安定しており経過観察不要
- グループB:やや不安定で経過観察が必要
- グループC:ずれがあり整復(骨の位置を戻す処置)が必要
- グループD:手術による固定が必要(プレートやピンなど)
この中で、グループC(整復のみ)の患者は、再骨折のリスクが他のグループよりも大幅に高く、
たとえばグループA(安定型)と比べて8倍ものリスクがあると報告されました。
手術でしっかり固定する治療(グループD)では、整復のみの治療よりも再骨折のリスクは低くなる傾向がありました。
このことから、ずれのある骨折を手術せず整復だけで治療した場合は、
骨が完全に強くなる前に再び折れるリスクが高まる可能性があります。
【再骨折を防ぐためにできること】
子どもの骨は自然治癒力が高く、通常はギプスなどの保存療法で十分に治ります。
しかし、以下のようなケースでは注意が必要です:
- 骨折部位にずれがある(整復が必要)
- 活発な運動をすぐに再開してしまう
- 成長中の骨の強度が十分でない
再骨折を防ぐには、治療後も慎重に経過を見守ることが重要です。
ギプスが外れたからといってすぐに激しい運動に戻るのではなく、
医師の指示に従って段階的に運動を再開するようにしましょう。
また、再骨折を経験した子どもは、再々骨折のリスクもあるため、より慎重な対応が求められます。
骨の健康を保つためには、カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動、日光浴なども日頃から意識しましょう。

【まとめ】
- 小児の再骨折率は約0.5%で、特に前腕の両骨折に多く見られます
- 再骨折は多くが1年以内に起こり、部位によってリスクや時期が異なります
- 治療法により再骨折のリスクは変わり、整復のみの治療ではリスクが高くなる傾向があります
再骨折を防ぐには、治療後の注意と経過観察が大切です。
保護者の皆さんは、治療が終わったあとも油断せず、お子さんの骨の回復をしっかり見守ってあげましょう。
【参考文献】
Pakarinen O, Ahonen M, Grahn P, Helenius I, Laaksonen T.
Refractures in Children. J Bone Joint Surg Am. 2025;107:e40(1-7).
https://doi.org/10.2106/JBJS.24.01014
免責事項
- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。
- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。
- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。
- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。
当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。