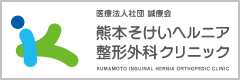元気になるオルソペディック ブログ
肩のケガで多い『肩鎖関節脱臼』とは?治療法と手術のタイミングを徹底解説
【肩鎖関節脱臼とは?症状と重症度分類】
肩鎖関節(けんさかんせつ)とは、鎖骨と肩甲骨(肩の骨)の一部である肩峰(けんぽう)をつなぐ関節です。肩の動きを支える重要な関節ですが、転倒やスポーツでの衝突により脱臼することがあります。

この脱臼を「肩鎖関節脱臼」と呼び、特に若いスポーツ選手に多く見られます。怪我の程度は「ロックウッド分類」と呼ばれる6段階の分類で評価されます。

- タイプI・II:靭帯が部分的に損傷している軽度なもの。
- タイプIII:完全に靭帯が断裂し、鎖骨が浮き上がる中等度。
- タイプIV〜VI:鎖骨が大きくズレている重度な脱臼。
痛みや肩の変形、腕の挙上困難などが主な症状で、診断にはX線が使われます。
【保存療法と手術の比較|どちらが良い?】
今回紹介する論文では、肩鎖関節脱臼に対する治療法について、過去の研究を整理した「システマティックレビュー」が行われました。特に以下の3つの観点から治療効果が比較されました。
- 手術と保存療法の比較
- 手術の時期(早期 vs 遅延)
- 解剖学的 vs 非解剖学的な手術手技の違い
● 手術と保存療法の違い
過去の14の研究をもとに、手術群706名と保存療法群369名が比較されました。結果は以下の通りです。
- 「良好」以上と判断された結果は、手術88%、保存療法86%とほぼ同等。
- ただし、手術群の方が関節の見た目(解剖学的整復)をより多く達成。
- 一方で、回復スピード(仕事やスポーツへの復帰)は保存療法の方が早いとされています。
つまり、見た目や整復度を求めるなら手術、早く復帰したいなら保存療法が選ばれる傾向にあります。

● ロックウッド分類ごとの基本方針
- タイプI・II:保存療法が基本
- タイプIII:まずは保存療法が推奨され、症状が続く場合は手術も検討
- タイプIV〜VI:手術が推奨される
【手術のタイミングと手技の選び方】
● 早期手術 vs 遅延手術
4つの研究では、早期(受傷から3週間以内)に手術を受けたグループの方が、結果が良好であることが多いと報告されています。
- 早期手術群の「良好」以上の結果:91%
- 遅延手術群の「良好」以上の結果:72%
ただし、これらの研究の多くが「レベルIII」のエビデンス(質がやや低い)であり、今後の高品質な研究が必要とされています。
● 解剖学的 vs 非解剖学的手術法
「解剖学的手技」とは、もともとある靭帯(円錐靭帯や台形靭帯)をできる限り元の位置・構造で再建する方法です。これに対し、「非解剖学的手技」は骨の位置関係だけを整える方法です。
以下の結果が示されています:
- 解剖学的手技での良好な結果:93%
- 非解剖学的手技での良好な結果:53%
再建靭帯の材質(自分の腱 vs 人工靭帯)による差も検討されていますが、どちらにも長所があります。
【まとめ:現時点での最適な治療戦略とは?】
肩鎖関節脱臼の治療は、患者さんの年齢・活動レベル・脱臼の程度によって異なります。今回の論文から得られるポイントを以下にまとめます。
- 軽度(タイプI・II):保存療法が第一選択
- 中等度(タイプIII):まずは保存療法、改善なければ手術
- 重度(タイプIV〜VI):手術が一般的
- 手術をするなら、できるだけ早期に行い、靭帯を解剖学的に再建する方法が望ましい
引用論文:
Beitzel K, Cote MP, Apostolakos J, et al. Current Concepts in the Treatment of Acromioclavicular Joint Dislocations. Arthroscopy. 2013;29(2):387-397.
免責事項
- 当ブログの内容はブログ管理者の私的な考えに基づく部分があります。医療行為に関しては自己責任で行って頂くようお願いいたします。
- 当ブログの情報を利用して行う一切の行為や、損失・トラブル等に対して、当ブログの管理者は何ら責任を負うものではありません。
- 当ブログの内容は、予告なしに内容を変更あるいは削除する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 当ブログの情報を利用する場合は、免責事項に同意したものと致します。
- 当ブログ内の画像等は、本人の承諾を得て、個人が特定されないように匿名化して利用させて頂いております。
当ブログでの個別の医療相談は受け付けておりません。